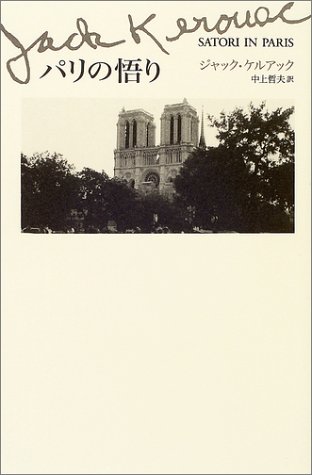ジャック・ケルアック『パリの悟り』/ 果ての地に始まりを探す旅
皆さんこんにちは。
今年も藤ふくろう氏(@0wl_man)の導きで、2年ぶりの開催となる海外文学 Advent Calendar 2022に参加することとなりました。
仏文50チャレンジは、いまだにプルーストの『失われた時を求めて スワン家のほうへ』を読んでいるところで、せっかくのプルースト没後100年という記念イヤーの波に全く乗ることができず、座礁してしまっています。年始にはなんとかしたい。
そのため今回は、仏文からは横道にそれますが、それでもフランスを通過するという視点から、ジャック・ケルアックの『パリの悟り』について感想を書いてみます。
和訳版が手に入らず、実際に読んだのは原著『Satori in Paris (Penguin Modern Classics)』の方。この文章を書いてる今知ったことですが、2022年はケルアック生誕100周年イヤーだった模様。
ちなみに今のところ一番最後の仏文50チャレンジ投稿である『夜の果てへの旅』の感想はこちらから。
あらすじ
1965年ジャック・ケルアックは、自身の祖先の地であるブルターニュへ赴くべく、フロリダからフランス・パリに到着する。ビールとコニャックに身を浸しながら、出会う人々と何気ない(あるいは意味のない)会話をかわしながら、パリからフランス北西の果てにある町ブレストへと旅をする。物語を通じて大きな展開が描写されるわけではないが、ケルアックは人との交わりや会話の中で、ふと「悟り」のような意識の目覚めを経験する。
***
本当に最近のことだが、ジャック・ケルアック(Jack Kerouac)がフランス・ブルターニュにルーツがあることを知った。改めて考えるとハッとするのだが、Kerouacという名前は非常にブルトンな名前のように思う。「Ker」はブルトン語で「家」や「集落」という意味で目にする機会も多く、さらに「ック」という語尾もブルターニュの地名を想起させる。
さらに作中でも語られるが、彼の本名Jean-Louis Lebris de Kérouacにある「Lebris」とはまさに「ブルトン人」の意味する言葉が名前に転用されたものだ。
そんなケルアックが自身のルーツを求めてこの地を訪問する自伝的小説があると知り、これはと思い読んでみた。
ちなみにケルアックは1965年5月に実際にブレストを訪れており、本書はその時の体験をベースにしているが、決して旅行記やルーツを巡るルポではなく、あくまで小説という体裁で書かれている。
また、ケルアックは本の中で「物語とは繋がり・交わりを語るために存在し、宗教的な何かあるいは畏敬を教え、文学が表現すべき現実の生活・現実の世界について伝えるもの」と定義を説明している。
実は、この本には「物語とは何を語るものなのか」というこの定義を小説内で表現するメタ的(?)な要素もあるのではないかと感じており、それは最後に書いてみたい。
ブルターニュへ
ケルアックのルーツがブルターニュにあるということは、(少なくともこの小説内で現れる)彼の人となりとの結びつきが認められる点で興味深い。
その一つは、酒だ。
フランス人が、ブルターニュの人々に抱くイメージの一つに「酒飲み」というものがある。
実際ワインやビールの消費量がフランス一なんだとか*1。

(右上のワインと左下のビールの週間消費量で国内一位になっている)
小説内で、ケルアックはビールとコニャックを時間を問わず飲んでいる。
ブレストでは、朝食からビールを飲もうとしていてホテルのスタッフに「え、正気ですか?」と聞かれてしまうほどだ。(ただ私が観測する限り、ブルターニュに限らずフランスで朝からバーでビールを飲んでいる人は実際にいる。)
なおケルアックは、この旅の4年後、『Satori in Paris』出版の3年後となる1969年、長年のアルコール摂取がもたらした肝硬変を起因とする静脈瘤の出血によって亡くなっている。
そしてもう一つはカトリック信仰だ。
ブルターニュは、歴史的にフランス国内でもカトリック信仰が厚い地域として知られている。
そしてケルアックといえば、「悟り」という言葉にも現れるように仏教や東洋思想への傾倒というイメージをなんとなく持っていたが、保守的とも言われるほどのカトリックであった点も指摘されている。
実際、この作品の中でケルアックは、キリスト教の教えや聖書の言葉を引用している。
そういえば、ブレストで自分と同じの姓をもつ「Ulysse Lebris」に会った際の「スポンジの酢は、渇きを殺す」という言葉は気になった。この言葉は、磔刑のイエスの最後の言葉「渇く」と酢に浸した海綿を口に押し当てられるという場面を想起させる。英文だけではうまく理解できなかったので今後和訳を参考にしたい。
それにしても、遠い昔に血を分けたかもしれない相手に「Ulysse」つまり「オデュッセイア」の名前をつけている点は見落としてはいけない点だろう。実際にケルアックが訪問したのは、書店と編集を営む「Pierre Le Bris」という名前だったらしい。
またパリのサン・シャペル(Sainte Chapelle)にルイ9世が収集した聖遺物聖十字架のかけらがあることを知っていたり、地元マサチューセッツで洗礼を受けた教会と同じ名前のサン・ルイ教会(おそらくEglise Saint-Louis-en-l'Île)があることを知っており、教会を訪問したいという気持ちを口にするものの、結局訪問することはなく旅は終わる。
信仰と行動が一致しない点は何を表しているのだろう。
果ての地とジレンマ
ブルターニュには他の地域にはみられない、独特の顔があると思う。
いつまでも降り続く雨と風にさらされる、孤独で深くどこまでも続く森と海の顔。人はその隙間にひっそりと生きている。
こういう地で、妖精や魔法の幻想奇譚が生み出されるのはよくわかる。その意味では岩手県の遠野と同じかもしれない。
ケルアックが訪ねたブレストは、ブルターニュの最西端にあり、フランス最大の軍港を擁する人口14万人ほどの中規模都市だ。
ブレストを含む行政地区Finistèreは、Finis(終わりの)+ tère(大地)と、文字通り「果ての地」という意味になる。
『パリの悟り』では、祖先のルーツを遡り様々巡るということはなく、基本はパリとブレストでの滞在とその道中しか描かれていない。
ケルアックには、そういった都市の風景ではなく、そのさらに奥にあるブルターニュ的な果ての地の風景の方がより心を打ったのではないだろうか。街の喧騒の届かない、より孤独で、心と自然の境界が失われてしまうような、深い霧の風景が。
しかしこの本を読むと、それも少し違うのかという気もしてくる。
ケルアックは、孤独の中にありたいのではなく、なんとしても自分の孤独と向き合い、正しく対処し、どうにかしてそれを解消したかったのかもしれない。
この「ケルアックの失敗」というタイトルの記事を見つけ、興味深く読んだのだが、ケルアックはとにかくジレンマに悩まされていたようだ。
戦後のアメリカで生まれる新たな生き方に憧れる一方、両親から受け継いでしまった伝統的な価値観やカトリシズムを捨て去ることはできない(父親は「ブルトン人であることを忘れるな」とよく言っていたそうだ)。
もっと根源的なところでは、フランス系カナダ人としてフランス人地区で生まれ育ち、小学校で初めて英語を学んだという出自から、「真にアメリカ人の男にはなれない」という失望もある。
そのためカウンターカルチャーとしてアメリカ社会に広がる禅や、カウンターポリティクスである共産主義を批判する一方で、東洋思想へあえて傾倒してみるなど、記事内で「ナルシシスティックな分裂」と表現されるジレンマがあったようだ。先ほどの信仰と行動が一致しない点も、おそらくそこに起因しているのではないだろうか。
そしてそのジレンマは、アルコール摂取量を増加させ、心身を蝕むことになり、「道の果てに行き着くのは、始まりの場所に帰ることだけ」となり、ケルアックはマサチューセッツの母の元に戻ることになるのである。
始まりの場所を求めることは、やがて祖先のルーツの探究にまで至ることになる。先に書いたが、ブルターニュという出自は、同じく酒飲みのカトリックであるケルアックにとってある意味運命的なものとして映ったのではないだろうか。その結果生まれたのがこの『パリの悟り』なのだ。

(ケルアックが訪ねた当時のブレストの写真。物語に出てくるシアム通りが写っている。*2)
悟りとは
結局のところ、「悟り」とはいったい何であったのだろう。
小説の冒頭に、フランス滞在中「突然の目覚め」を得た様々な場面が列記されているが、その最初には「アメリカ帰国のためパリからオルリー空港に向かう際のタクシードライバー、レイモン・バイエ(Raymond Baillet)から渡された」とある。
そのレイモン・バイエが出てくるのは小説の一番最後。ケルアックを乗せ、一緒にビールを飲み、その後空港まで送り、そして別れるだけの存在なのだ。
二人が交わす最後の会話を見てみると、
バイエ
「今日は日曜日だってのに俺は妻と子供を養うために働いているんだ。で、あんたから子供が20人やら25人やらいるケベックの家族の話を聞いたけど、それは多すぎさ。俺は二人だけ。でも働かないと。そうさ。これもやってあれもやって。ムッシューの言う通り、ディスもザットもさ。とにかく、ありがとう。元気で。俺は行くよ。」
ケルアック
「さようなら、ムッシューレイモン・バイエ」
これが1ページ目に書いた悟りのタクシードライバーだ。
神が「私は生かされている」と言うとき、俺たちはそれまでの別れがなんだったかみんな忘れちまっている。
とある。
ここで、最初に記したケルアックによる文学の定義が想起させられる。
「物語とは繋がり・交わりを語るために存在し、宗教的な何かあるいは畏敬を教え、文学が表現すべき現実の生活・現実の世界について伝えるもの」
バイエは「現実の生活、現実の世界」について話している。よく知られているがフランスでは日曜日は休息の日だ。それでも家族を養うために彼は働かなくてはならない。
現実について、そして人と繋がることについて伝えるということ。バイエの存在と言葉は、その芯をついている。
『パリの悟り』という作品自体が、繋がりを求めフロリダからフランスまでやってきた男が様々な霊感を得ながら、現実についてその厳しさも合わせて伝えている物語なのだ。
結局それこそが「悟り」なのだろう・・・か。
残念ながら、最後の「神が「私は生かされている(I Am Lived)」と言うとき・・・」という文は、まだ理解し切れていない。ケルアックはバイエの言葉から、宗教的な解釈を導いているのだと思うのだけど、そもそも「I Am Lived」はどこからの引用なのだろう。
また面白いのは、バイエはフランスの中南部オーヴェルニュ(Auvergne)出身だという。
それまで旅したブルターニュはいったいどこに行ってしまったのか。
しかしそれで良いのだ。
ルーツを同じくするものだけが自分の心を温めてくれるわけではない。
偶然出会いわずか数時間だけを共にした誰かが、繋がりを、悟りをもたらすことだってあるのだから。
最後に
以下の文章2つは、本の中でとても気に入ったのでぜひ引用してみたい。
Yet this book is to prove that no matter how you travel, how ‘successful’ your tour, or foreshortened, you always learn something and learn to change your thoughts.
「うまく進もうが短くなろうが、どんな旅であれ、お前はいつも何かを学び、自分の考えを変えることを学ぶ。この本はそれを証明するものだ。」
As I grew older I became a drunk. Why? Because I like ecstasy of the mind. I’m a Wretch. But I love love.
「歳をとるにつれ、酒飲みになった。なぜだろう。それは、意識による恍惚が好きだからだ。俺は哀れなやつだな。でも愛っていうものが好きなんだ。」
ブルターニュの深い森や海とケルアックがどう対峙するのだろうと想像していたら、まるで違うほぼ都市の話だったので笑ってしまったのだが、フランス文学とは違う勢いやリズムがあり、あっという間に読める内容だった。
ケルアックは他にも、フランス系アメリカ人のアイデンティティを軸とした作品もあるようで、他の作品も読んでみたい。
【2021年振り返り】フランス文学ベスト50チャレンジ一年目の経過
2020年末にはじめたフランス文学ベスト50読破チャレンジも一年が過ぎたので、一度経過を見てみる。
読了し感想まで書けた作品に色をつけてみると、以下の通り。
| タイトル | 作者 | 刊行年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 悪の華 | シャルル・ボードレール | 1857 |
| 2 | レ・ミゼラブル | ヴィクトル・ユーゴー | 1862 |
| 3 | 異邦人 | アルベール・カミュ | 1942 |
| 4 | 危険な関係 | ピエール・ショデルロ・ド・ラクロ | 1782 |
| 5 | 星の王子さま | アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ | 1943 |
| 6 | 夜の果てへの旅 | ルイ=フェルディナン・セリーヌ | 1932 |
| 7 | ボヴァリー夫人 | ギュスターヴ・フローベール | 1857 |
| 8 | シラノ・ド・ベルジュラック | エドモン・ロスタン | 1897 |
| 9 | 赤と黒 | スタンダール | 1830 |
| 10 | ベラミ | ギ・ド・モーパッサン | 1885 |
| 11 | カンディード、あるいは楽天主義説 | ヴォルテール | 1759 |
| 12 | モンテ・クリスト伯 | アレクサンドル・デュマ・ペール | 1844 |
| 13 | 三銃士 | アレクサンドル・デュマ・ペール | 1844 |
| 14 | 日々の泡 | ボリス・ヴィアン | 1947 |
| 15 | アンチゴーヌ | ジャン・アヌイ | 1944 |
| 16 | 失われた時を求めて | マルセル・プルースト | 1927 |
| 17 | 寓話 | ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ | 1678 |
| 18 | ジェルミナール | エミール・ゾラ | 1885 |
| 19 | ゴリオ爺さん | オノレ・ド・バルザック | 1835 |
| 20 | ノートルダム・ド・パリ | ヴィクトル・ユーゴー | 1831 |
| 21 | ペスト | アルベール・カミュ | 1947 |
| 22 | フェードル | ジャン・ラシーヌ | 1677 |
| 23 | オルラ | ギ・ド・モーパッサン | 1887 |
| 24 | スワン家のほうへ | マルセル・プルースト | 1913 |
| 25 | 死刑囚最後の日 | ヴィクトル・ユーゴー | 1829 |
| 26 | ドン・ジュアン | モリエール | 1665 |
| 27 | ボヌール・デ・ダム百貨店 | エミール・ゾラ | 1883 |
| 28 | 海底二万里 | ジュール・ヴェルヌ | 1869 |
| 29 | 居酒屋 | エミール・ゾラ | 1877 |
| 30 | 感情教育 | ギュスターヴ・フローベール | 1869 |
| 31 | 女の一生 | ギ・ド・モーパッサン | 1883 |
| 32 | ル・シッド | ピエール・コルネイユ | 1637 |
| 33 | ガルガンチュワ物語 | フランソワ・ラブレー | 1534 |
| 34 | 守銭奴 | モリエール | 1668 |
| 35 | ランボー全詩集 | アルチュール・ランボー | 1895 |
| 36 | 静観詩集 | ヴィクトル・ユーゴー | 1856 |
| 37 | 幻滅 | オノレ・ド・バルザック | 1839 |
| 38 | マルドロールの歌 | ロートレアモン伯爵 | 1869 |
| 39 | アンドロマック | ジャン・ラシーヌ | 1667 |
| 40 | クレーヴの奥方 | ラファイエット夫人 | 1678 |
| 41 | パリの憂鬱 | シャルル・ボードレール | 1869 |
| 42 | アルコール | ギヨーム・アポリネール | 1913 |
| 43 | ロレンザッチョ | アルフレッド・ド・ミュッセ | 1834 |
| 44 | あら皮 | オノレ・ド・バルザック | 1831 |
| 45 | パルムの僧院 | スタンダール | 1839 |
| 46 | 獣人 | エミール・ゾラ | 1890 |
| 47 | 運命論者ジャックとその主人 | ドゥニ・ディドロ | 1778 |
| 48 | グラン・モーヌ | アラン=フルニエ | 1913 |
| 49 | 八十日間世界一周 | ジュール・ヴェルヌ | 1873 |
| 50 | テレーズ・ラカン | エミール・ゾラ | 1867 |
読み終わっている本は他にもあるが、感想まで書けたのは10冊。
『モンテ・クリスト伯』や『三銃士』など、なんとなくストーリーは知っているがちゃんと読んだことがなかった作品を読了できたのは良かった。あとモンテ・クリスト伯なら南仏、三銃士ならラ・ロシェルとユグノー戦争から続くフランスの宗教対立など、フランスの地理や歴史と結びつけられるのも良い点だろう。
2021年に読んだものでのベストは、やはり昨年最後に読んだ『夜の果てへの旅』だろうか。
パラダイムシフトのような作品なので、一度自分の中で整理させておかないと、これから読む作品の印象が変わってしまいそう。
上位5作は最後に読もうと思っているので、2022年は16位に控えるプルースト祭りになること間違いなし。
岩波文庫の吉川一義訳を揃えたが、全部で14巻ある・・・!『モンテ・クリスト伯』の2倍である。全部で7編なので、1編ずつ感想を書いていこうかと考えている。
前にも書いた通り、ランキングはこのサイトにあるものを借用している。今見ても順位が変わっているので、私が見た1年前の順位であることを注記しておきたい。
ところでフランスではこの1月にすでに500冊以上の小説が新たに刊行されたらしい。その中で一番話題とも言える、ミシェル・ウエルベックの700ページを超える長編新刊『anéantir』が発売となったので早速買ってみた。辞書を片手にこちらも読んでみたい。
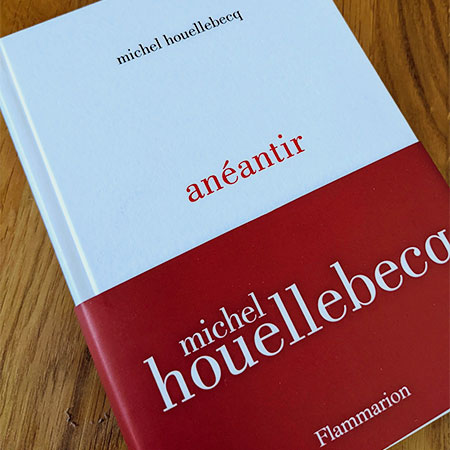
セリーヌ『夜の果てへの旅』/ 悪意の泥沼を進み続ける厄祓いの物語
仏文50チャレンジ第10回の感想は、第6位の『夜の果てへの旅』(中公文庫、生田耕作 訳)についてです。今回も物語の結末が含まれています。
前回『ボヴァリー夫人』の感想はこちらから。
あらすじ
パリの通りを行進する軍隊に気まぐれのごとく参加したフェルディナン・バルダミュは、第一次世界大戦の戦地へと送られる。食糧が乏しく眠ることが許されない激戦地の過酷な経験の中、脱走兵のレオン・ロバンソンと出会う。
負傷によりパリに戻ったフェルディナンは、アフリカ、アメリカ、再びフランスと生きる場所を変える。行く先々で再会するロバンソン、そして各地の人々の現実とそこに渦巻くあらゆる感情や欲望を語りつつ物語は進んでいく。
悪意の泥沼を進む
人間は皆意地悪だ、それ以外のものは人生の途中でどっかへ消えちまったんだ
本作『夜の果てへの旅(Voyage au bout de la nuit)』は、2つの大戦の間である1932年に医師であったルイ=フェルディナン・セリーヌにより発表された。
巻末の解説にて訳者の生田耕作氏が、「現代社会の病根を完膚なきまでに摘出した」と評する通り、本作は作者と同じ名を持つフェルディナンが、第一次世界大戦中と戦後の世界が内包する邪悪さを徹底的に語り尽くす作品だ。
アフリカでは植民地主義、アメリカでは資本主義、ヨーロッパにおける戦争。
そこには、そのイズムの中で成立する均衡が存在する。
アフリカでは白人は黒人をモノのようにこき使うが、実は黒人側にも白人を利用する側面が見られる。そういった人間の歪な均衡の中、フェルディナンを苦しめるのは毛虫やしらみ、赤蟻という「取るに足らない」存在であるのが面白い。
「取るに足らない」ものにこそ邪悪さがある。
フェルディナンは旅のごとく、そして逃亡するがごとく世界を駆け巡っているが、物語そのものにおいては実は淡々と日常が進んでいく。
僕は自分の悪癖の、到るところから逃げ出したい欲望を愛していた。
人が仕事をし、食べ、娯楽をもち、色に溺れる。
人間の邪悪さを見るには、何も戦争のような極限状態にある必要はない。何よりこの作品内で戦争の直接的描写は非常に少ない。
むしろ日常にこそそれは普遍していることをフェルディナンは暴いていく。
その意味で、この作品は究極の日常系小説と言っても良いかもしれない。
例えばどんな人間がいるかというと、
・前線送りを免れパリにいたにもかかわらず、帰還兵に張り合うように「こっちもひどかった」と語る宝石商。
・根拠なくフェルディナンの悪評を流布し、彼が殺されるように仕向ける女教師。
・母性本能を満たすべく子供の支援をするが、そのカゲで「あたしが欲しいのはあんな慕われ方じゃない」と子供にケチをつける女。
・厄介な母親を疎んじ、ついには殺してしまおうと考える夫婦。
嫉妬、見栄、恨み、軽蔑、偏見、傲慢。
単純な悪ならまだしも、こういう心をえぐるタイプの悪意はタチが悪い。
フェルディナンが足を踏み入れるのは、いつもこういった悪意の泥沼である。そしてその悪意の沼から離れようとはせず、ただ進み続ける。
それなら、その先で出会う人々から悪意が浮かび上がったとしても驚くことではない。
厄祓いの物語
セリーヌの研究者である杉浦順子氏のテキストによると、1930年3月『夜の果ての旅』執筆中であったセリーヌは、友人に向けて以下のように書いているそうだ。
まずは戦争、他のすべてはそれ次第で、まずはこの厄を祓うのが問題です*1。
作者セリーヌは1912年、18歳の時にフランス軍に入隊している。1914年、第一次世界大戦開戦後に西フランドルの戦地に送られ、同年10月に負傷。この怪我により戦闘不適格とされ除隊することになる。
それから15年経った1930年に、戦争経験の厄祓いとして『夜の果てへの旅』の執筆が言及されているのだ。大戦への従軍はわずか1-2年足らず(うち、前線への従軍はおそらく数ヶ月程度)であったはずだが、それがいかにセリーヌにとって大きな経験であったかがうかがえる。

J. Coutas, Public domain, via Wikimedia Commons
この物語は、戦争により始まり、数々の再会ののちロバンソンの死で幕を閉じる。
ここで興味深いのは、国民射的場(tirs des nations)という、つまりは祭りの射的が作中のはじめと終わりで2度出てきていることだ。
1度目は戦場からパリに戻った際、恋人と遊びに行った祭りに登場し、フェルディナンは戦争のフラッシュバックを起こし発狂する。
「みんな逃げるんだ!」大声で僕は警告を喚き立てた。「逃げるんだ!撃たれるぞ!殺(ばら)されるぞ!みんな殺されるぞ!」
2度目はそれから15年後、再びパリでフェルディナンとロバンソン、それぞれの恋人と遊びに出かける時に登場し、ここでは発狂は生じない。
しかし、その代わり、ロバンソンは恋人に銃で撃たれてしまう。
フェルディナンは、「旅とは、結局このとるにたらぬしろもの、いくじなしのための小さな眩暈の追求だ」と言っているが、戦争後の15年の旅路で積み重ねた「小さな眩暈」は、少なくともフェルディナンを発狂から防ぎ、自己の回復に導いた。
そして、2度目にロバンソンが撃たれ命を落とす。
ロバンソンは、フェルディナンが「そこにいる」と思う先に必ず現れる。実は所々で「ロバンソンは本当に存在するのか、あるいはフェルディナンの妄想か」とその存在が疑わしくなる箇所もある。
戦場でフェルディナンに亡霊のごとく取り憑いたロバンソンが、ついに消えてしまう。
戦争の狂気が完全に取り祓われたと言い切ることはおそらく難しいだろう。が、かくして作中における厄祓いの試みは為されたのだ。
ちなみに杉浦氏は
一時的に失明したロバンソンは、一旦はマドロンと恋に落ちるが、再び視力を取り戻すと、この関係から逃げ出そうとして彼女に殺される。この恋愛ドラマには、明らかに愛国主義戦争に盲目的熱狂で加わった14年の兵士のドラマとが重ねられている。
と指摘している*2。
ロバンソンはフェルディナンの分身であると同時に、大戦に関わり喪失と裏切りを経験したあらゆる兵士の投影でもあるというこの指摘は、この「厄祓い」の物語にさらなる厚さと重さを生み出している。
今セリーヌが語られる文脈
セリーヌといえば、作者のネガティブな評価を作品も引き継ぐか、あるいは切り離されるべきか、という問いにおいて名前が挙げられる筆頭格だ。
セリーヌの場合、作者を正面から評価することは困難でありつつ、その著作の評価はフランス文学の重要作品の一つとして不動の域に達している。実際、本屋から作品が撤去されることはなく、2021年は没後60周年ということもあり、大手書店で一目につきやすい場所に陳列されているのも見かけた。しかし、晩年の生家の公的な保存や美術館・資料館化は今尚困難であるようだ*3。

上部に船が彫られている。
Ferdinand.bardamu, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
本作では、大戦後の世界、人間、社会が持つあらゆるグロテスクさを暴き続けるその眼差しこそが作品を動かし続ける。
野心や大恋愛、大河的人生や復讐など、大義で裏打ちされた、いわば正統とも言えるようなフランス文学作品をこの一年読んできたが、『夜の果てへの旅』にはそれらを過去のものにするだけの力があった。
おそろしく強烈な一冊だった。
*1:「戦争とメランコリー、あるいは新世紀病 一L−F.セリーヌの『夜の果ての旅』読解一」、杉浦順子、関西フランス語フランス文学、2005、11巻、p.40
*2:杉浦、p.46
*3:La maison de Céline, emblème de la réhabilitation impossible d’un écrivain maudit